情報商材は、知識やノウハウなどの「情報」そのものを商品化したものを指します。投資やスキル習得を目的に販売されるケースが多いですが、なかには実態のない詐欺まがいの商材も少なくありません。
高額な費用を支払ったものの成果が出ず、返金もされないまま不安や後悔を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、情報商材詐欺の代表的な手口をはじめ、被害に遭ったときの相談先や返金方法を詳しく解説します。弁護士へ相談すれば返金できる可能性が高まるので「もしかして詐欺かも?」と感じている方は、法律事務所Zへお気軽にご相談ください。
【監修】

| 伊藤 建(いとう たける) 消費者庁出身・法律事務所Z代表弁護士 2011年に国家公務員第Ⅰ種試験、司法試験にダブル合格。多くの詐欺被害案件を手掛け、被害額数100億円の大規模詐欺事件でも勝訴判決を得る等の実績を有する。 |
情報商材とは

情報商材とは、副業や投資などに関する知識・ノウハウを商品化したものを指します。主にデジタルコンテンツとして提供され、購入者は会員制サイトや動画などで学習できる仕組みです。
情報商材は効率よく知識を得る手段になり得ますが、なかには内容の信頼性や効果が実証されていないものも存在します。悪質な販売者は、アフィリエイトでの宣伝を活用して購入者を誘導することが多いため注意が必要です。
社会全体がデジタル化に向かうなか、情報商材に関するトラブルも増加傾向にあります。詐欺被害に遭わないためにも、情報商材を購入するときは慎重に検討することが大切です。
情報商材詐欺の見分け方|代表的な手口5つ

情報商材詐欺に遭わないためには、以下の典型的な手口を知っておくことが重要です。
- SNSでアフィリエイターが勧めている
- 誇大広告が見られる
- 希少価値をほのめかして購入を促してくる
- 無料特典から高額商材を提案してくる
- 返金保証を謳っている
悪質な情報商材は一見すると魅力的でも、実際には内容が薄かったり再現性が低かったりすることも珍しくありません。本章では情報商材詐欺の手口を詳しく解説します。
1. SNSでアフィリエイターが勧めている
アフィリエイターとは、企業の商品やサービスを自身のSNSで紹介し、そこから発生した成果(購入や申し込み)に応じて報酬を得る人のことです。
情報商材は高額な報酬につながりやすいため、実績を誇張して商材を宣伝するアフィリエイターも少なくありません。「誰でも簡単に稼げる」「初月から元が取れた」といった言葉で、強く勧めている情報商材は特に注意が必要です。
アフィリエイターの投稿は広告目的で作られており、実際の効果を示すものではありません。販売ページの情報や外部の口コミも確認しながら、慎重に検討しましょう。
2. 誇大広告が見られる
誇大広告が見られることも、情報商材詐欺の手口のひとつです。過大な成果を強調することで購買意欲を煽り、実際には提供できない内容で高額な費用を請求してきます。
「1日数分の作業で月収100万円を実現できる」「初心者でも必ず成功する」など、現実的に実現不可能な広告が見られる場合は、信頼できる情報商材といえません。優良な情報商材は、断定的な表現を避け、学習のステップや到達できるスキルを明確に示しています。
広告の文言が過度に魅力的で具体性に欠けているときは、いったん立ち止まって冷静に情報を整理しましょう。
3. 希少価値をほのめかして購入を促してくる
情報商材詐欺では、希少価値をほのめかして購入を急がせる手口も多く使われています。「今だけ限定」「残りわずか」といった言葉で冷静な判断を妨げ、焦って契約を決断させるのが狙いです。
なかには「この情報は極秘」「このルートでしか手に入らない」といった特別感を演出し、購入者に価値があると思わせるケースもあります。正当な販売でも使われる手法ですが、過度に強調されている場合は、根拠となる情報をよく調べることが大切です。
4. 無料特典から高額商材を提案してくる
無料特典を入口にして高額な商材を提案してくるのも、情報商材詐欺の典型的な手口です。無料プレゼントや無料セミナーといった特典で消費者の関心を引き、後から「より稼ぐためにはこの商品が必要」と高額な商材を提案してきます。
無料特典自体は軽いノウハウや体験版であり、本命は高額で内容が不透明なバックエンド商品であるケースが一般的です。購入者は最初の無料感覚から大きな出費に至りやすく、気付かないうちに数十万円以上請求されることもあります。
購入後も、メルマガや電話で囲い込みを受けるリスクがあるので、無料特典を謳った情報商材には十分注意しましょう。
5. 返金保証を謳っている
返金保証を掲げて安心感を与え、購入のハードルを下げる手口です。情報商材詐欺では「全額返金可能」と明記されていても、実際には返金条件が極端に厳しかったり、問い合わせても応答がなかったりする事例が見られます。
情報商材は無形かつ購入後の複製が容易なので、販売者から見ると返品はほとんど意味をなしません。返金保証制度を悪用し、購入を促しているだけの可能性もあるため、安易に信じすぎないようにしましょう。
情報商材詐欺に遭ったときの相談先
情報商材詐欺は、民法・消費者契約法・特定商取引法といった法律違反になり得ます。詐欺被害に遭った場合は、以下のような専門機関に相談可能です。
- 弁護士
- 司法書士
- 消費生活センター
早めの相談で返金できる可能性が高まるので、1人で抱え込まず、まずは問い合わせてみましょう。
弁護士
情報商材詐欺の被害に遭ったとき、もっとも頼りになるのが弁護士です。弁護士は、返金請求から損害賠償請求、訴訟まで法的手続きに一貫して対応できます。
また、弁護士には守秘義務があるため、個人情報や詐欺被害が外部に漏れる心配はありません。落ち着いて状況を整理し、被害の回復につなげられます。
早期の相談が成功率を高めるため、被害に気付いたらできるだけ早く弁護士に相談しましょう。ただし弁護士事務所の中には、お金だけをだまし取る悪徳な事務所もあります。二次被害に遭わないためのポイントは、以下の記事でチェックしてみてください。
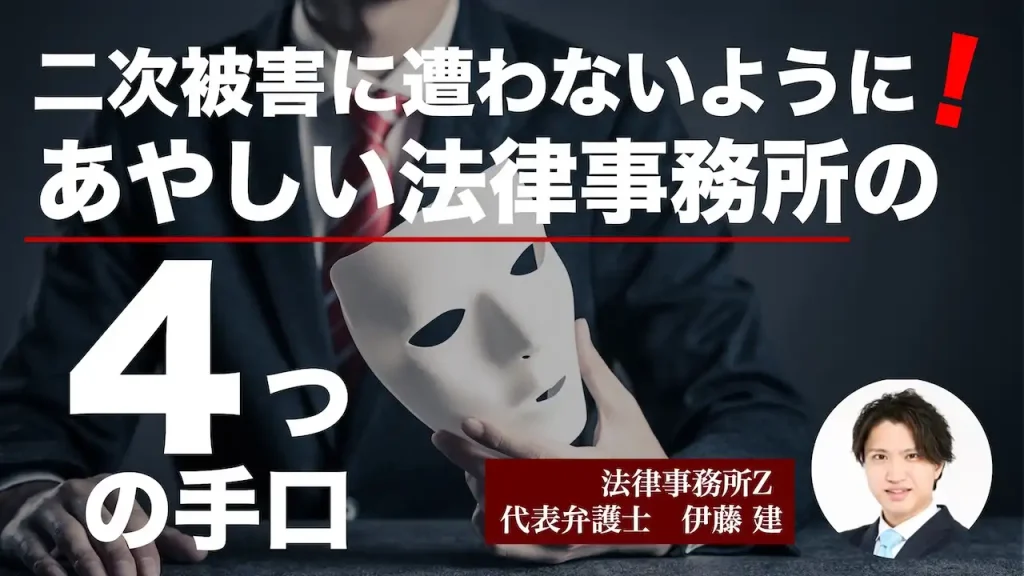
法律事務所Zなら相談料無料で被害回復をサポート
法律事務所Zでは、相談料・着手金無料で情報商材詐欺の相談が可能です。経験豊富な弁護士が被害の状況を丁寧にヒアリングし、最適な返金請求や法的手続きをサポートいたします。ご依頼時は弁護士が直接面談を担当するので、安心してご相談ください。
- 情報商材詐欺に遭ったかもしれない
- 返金できるのか知りたい
- 詐欺被害に遭ってどうすればよいかわからない
このような悩みをお持ちの方は、以下から気軽にお問い合わせください
司法書士
司法書士も、情報商材詐欺を相談できる窓口のひとつです。返金交渉や悪徳業者の調査に対応しており、弁護士に依頼するよりも比較的費用を抑えながら被害回復を目指せます。
また認定司法書士であれば、140万円以下の民事案件に限り、簡易裁判所での訴訟支援も可能です。「返金交渉が長引いている」「証拠書類の整理や申立てが難しい」という場合は、司法書士に相談することでスムーズな手続きを実現できるでしょう。
消費生活センター
消費生活センターは、各自治体に設置されている公的機関です。情報商材をはじめ、消費者が商品やサービスの購入でトラブルを抱えた場合に無料で相談できます。
消費生活センターでは専門のスタッフが相談を受け、助言や情報提供を行います。必要に応じて弁護士や司法書士といった専門家につないでくれるので、刑事事件に至らない初期の相談にぴったりです。
電話相談は「188」の消費者ホットラインで対応しており、誰でも気軽にアクセスできます。ただし法的代理権はないため、返金請求や訴訟を求める場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
情報商材詐欺に遭ったときの返金方法6つ

情報商材詐欺に遭ったときの返金方法には、以下のように複数の手段があります。
- 販売事業者に対する返金請求
- 決済代行会社への返金請求
- 銀行口座凍結の要請
- チャージバックの申請
- 支払停止の抗弁
- 訴訟による返金請求
被害の状況や購入形態によって適切な返金手段が異なるため、まずは自分がどの方法でアプローチするべきか整理することが大切です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 販売事業者に対する返金請求
情報商材の広告や販売サイトに「返金保証」の文言があれば、販売事業者に対して返金請求が可能です。
情報商材の内容を正しく実行しても成果が出なかった場合、優良な業者であれば返金してもらえる可能性があります。返金請求をするときは、契約書や購入時の画面、販売ページのコピーなどを保存しておくことが重要です。
ただし悪質な事業者は返金に応じないことが多く、連絡を無視したり曖昧な回答を繰り返したりするケースもあります。返金を拒否された場合は、具体的なやりとり内容を残しておき、別の方法を検討しましょう。なお、販売事業者に返金を求めても応じない場合は、内容証明郵便を利用して返金請求を行う方法があります。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは「いつ誰が誰にどのような内容を送ったか」を郵便局が公的に証明するサービスです。
内容証明郵便を使えば、返金請求の正当性や本気度を相手側に示すことができ、法的な牽制手段として役立ちます。具体的には以下のような項目を明記し、「返金に応じない場合は法的手段を講じる」とはっきり伝えるのがポイントです。
| 【請求書に記載すべき項目】契約の履行状況(契約年月日、商品名、金額)返金を求める理由返金期限返金請求の根拠となる法令返金先の銀行口座 |
返金を主張する法的根拠としては、例えば、民法96条や民法709条に基づくものがあります。消費者契約法・特定商取引法といった法律違反にもなりうるので、弁護士等の専門家に相談することが望ましいでしょう。
内容証明郵便自体に強制力はないものの、相手側にプレッシャーを与える効果はあります。今後の法的手続きにおける証拠にもなるので、交渉力を高める手段としても検討してみてください。
3. 決済代行会社への返金請求
販売事業者が返金に応じなかったり、連絡が取れない場合は、決済代行会社へ返金請求するのもひとつの方法です。決済代行会社は情報商材の内容を審査したうえで決済を代行し、利益を得ています。
販売事業者が詐欺商材だった場合は、決済代行会社も法的な責任を負うため、返金にも応じてもらえる可能性があります。内容証明郵便での返金請求が基本ですが、対応の可否は代行会社によって異なるので注意が必要です。
4. 銀行口座凍結の要請
情報商材の代金を銀行振込で支払った場合は、振込口座の凍結を要請できます。振り込め詐欺救済法に基づく被害者救済制度で、凍結した口座に資金が残っている場合は、被害額に応じて分配を受けることが可能です。
銀行口座の凍結を要請するときは、入金を指定された金融機関に被害を申告します。詐欺被害に気付いたら早めに連絡し、詐欺に遭った経緯や振込額などを明確に伝えましょう。
ただし、凍結時に口座に残高がなければ実質的な返金は期待できません。あくまでも被害拡大を防ぐ手段と考え、並行して弁護士へ相談することが大切です。
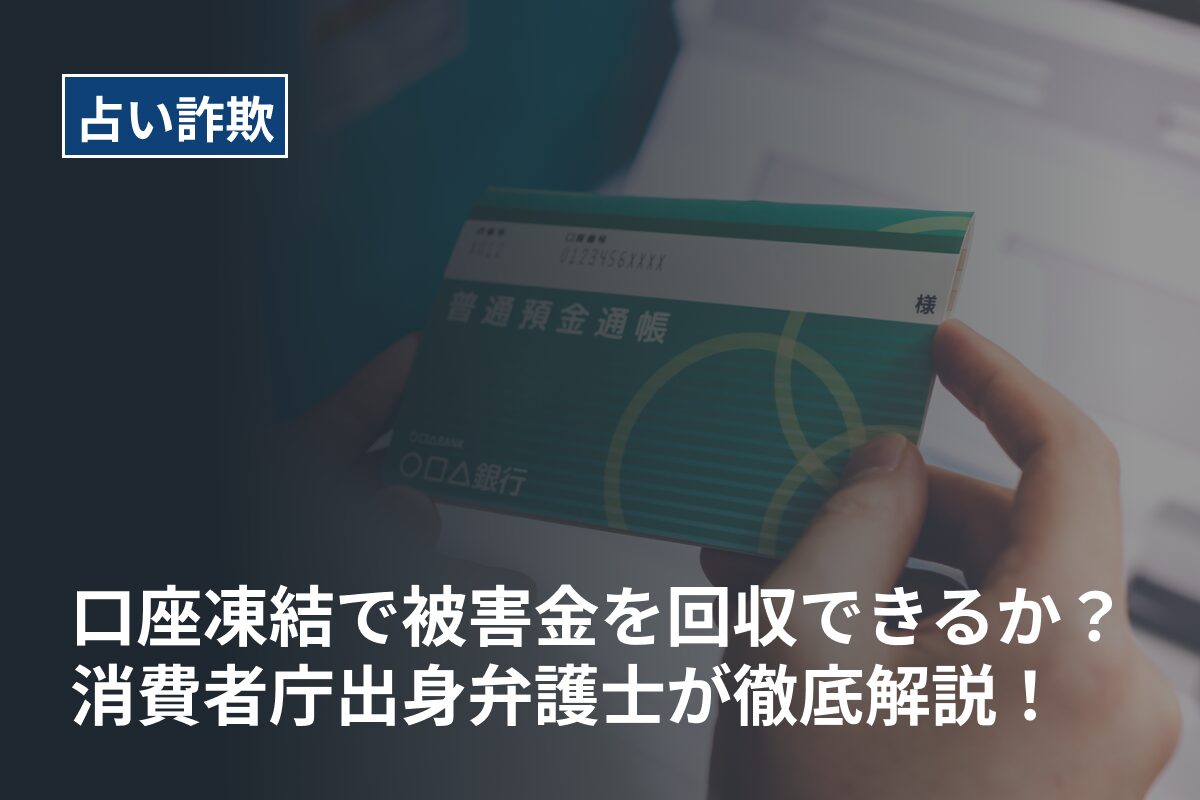
5. チャージバックの申請
クレジットカード(一括)で情報商材を購入した場合は、チャージバックの申請を検討してみましょう。チャージバックとは、消費者が不正取引に遭った場合に、カード会社を通じて支払いを取り消してもらえる仕組みです。
クレジットカード会社に情報商材詐欺の被害が認められれば、支払い義務がなくなり、返金を受けられます。チャージバックの判断は各カード会社に委ねられるので、申請時は販売事業者とのやり取りや詐欺の証拠を提出することが大切です。
カード会社によって申請期限が設けられているため、被害に気づいたら早めに行動することをおすすめします。
6. 支払停止の抗弁
情報商材をクレジットカードの分割払いやローン契約で購入した場合は、支払停止の抗弁という制度を利用できる可能性があります。支払停止の抗弁とは、取引の契約に瑕疵や詐欺があった場合に決済の停止を求められる権利です。
クレジットカード会社に「支払停止の抗弁に関する申出書」を提出し、申請が認められれば以後の分割払いやローン支払いをストップできます。チャージバックと同じく、詐欺被害の証拠が必要なので、難しい場合は弁護士の支援を得ながら進めるとよいでしょう。
7. 訴訟による返金請求
内容証明郵便を使っても返金に応じない場合は、訴訟による返金請求が最終手段となります。被害額が60万円以下の場合は「少額訴訟」という手続きを利用可能です。少額訴訟は原則1回の審理で判決が下されるため、通常の民事訴訟よりも迅速かつ費用を抑えて解決できるメリットがあります。
請求額が60万円を超える場合は、簡易裁判所や地方裁判所における通常の民事訴訟となり、訴状や証拠の提出、複数回の審理を経て裁判官が判断します。勝訴すると損害賠償や返金を命じてもらえますが、相手に資産がなければ回収できないため注意しましょう。
また訴訟には、証拠の提出や専門的な手続きが必要なので、弁護士に依頼するのが一般的です。詐欺被害に強い法律事務所を選ぶことで、訴訟もスムーズに進められます。
情報商材はクーリング・オフできる?
特定商取引法の要件を満たしていれば、情報商材のクーリング・オフは可能です。以下の取引には、8日間のクーリング・オフ期間が設けられており、期間内であれば違約金を払わずに解約できます。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
- 訪問購入
※連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日以内でクーリング・オフが可能
ただし、インターネットを通じて購入した情報商材は「通信販売」に分類され、クーリング・オフの対象外となります。「自らの意思で購入した」と判断されるため、返金を求める場合は直接交渉しなければいけません。
とはいえ、電話で勧誘されたりセミナーで直接購入したりした場合は、クーリング・オフの対象となる可能性もあります。判断に迷う場合は、弁護士や消費生活センターに相談することが大切です。
情報商材詐欺の返金請求なら法律事務所Zへ相談を
情報商材は正しく活用すれば自己投資となりますが、残念ながら詐欺的な手口で高額な商品を売りつける悪質業者も少なくありません。購入後の返金が難しいため、被害を回復するには法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
私たち法律事務所Zは、年間1,000件以上の詐欺に関するご相談をいただいており、多くの返金実績がございます。消費者庁出身の弁護士 伊藤建をはじめ、複数の弁護士が返金交渉までサポートいたします。相談料・着手金は一切かかりません。
詐欺サイトの運営者との返金交渉ノウハウも蓄積されておりますので、安心してご相談ください。


 電話で相談する
電話で相談する メールで相談する
メールで相談する LINEで相談する
LINEで相談する
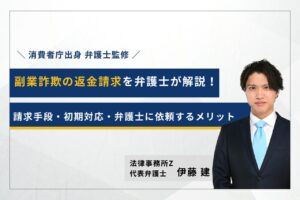
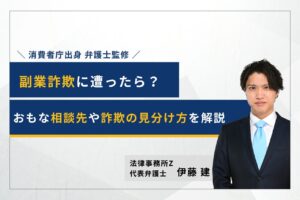
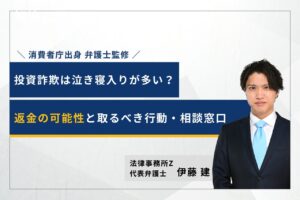
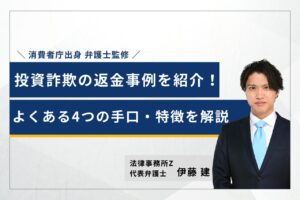
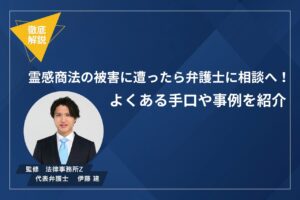
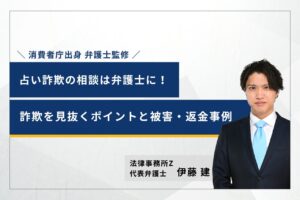
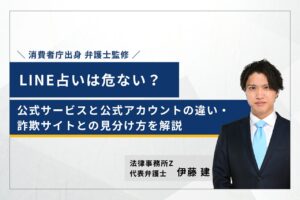
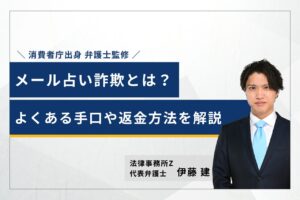

コメント
・ご入力いただいた名前、メールアドレス、電話番号は公開されませんので、ご安心ください。
・ご入力いただいたコメントは弊所で内容を確認の上、公開させていただきます。公開まで少々お待ちください。